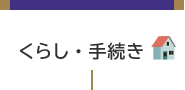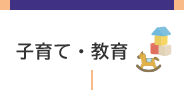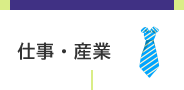ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
被災家屋等の解体・撤去について(公費解体)
令和6年能登半島地震による公費解体の状況
令和6年能登半島地震により被害を受けた家屋等を所有者に代わって町が解体・撤去する「公費解体制度」について、穴水町では令和7年1月31日に新規の申請の受付を終了し、申請を受理した解体・撤去工事を鋭意進めておりましたところ、同年10月31日をもって同制度による解体・撤去工事が完了しました。穴水町における公費解体制度により解体・撤去した棟数は、住家757棟、非住家1,985棟の全2,742棟でした。
下図に町内の公費解体実施建物の分布を示します。この分布から、令和6年能登半島地震による建物被害が町内全域にわたって生じており、特に市街地中心部や沿岸部での被害が大きかったことがわかります。

穴水町における公費解体実施建物の分布 [PDFファイル/307KB]