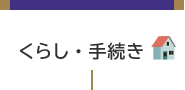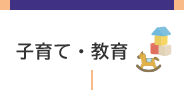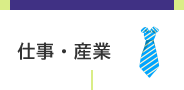本文
介護サービス費用と利用の目安について
介護サービス費用と利用のめやすについて
サービスの利用者負担について
利用者はケアプランにもとづいて介護保険サービスを利用し、実際にかかるサービス費用の一部を支払います。また、利用するサービスによっては、別に食費・居住費や日常生活費などが必要となる場合や、介護保険の対象とならないサービス費用もあります。
利用者負担の割合
利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割、または3割です。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されていますので、ご確認ください。
| 3割 |
下記の両方に該当する人
|
| 2割 |
上記「3割」の対象とならない方で、下記の両方に該当する人
|
| 1割 |
上記以外の人 |
介護(予防)サービスの費用について
介護保険のサービスを利用するときは、かかった費用の1割、2割、または3割を負担しますが、介護度に応じて利用額の上限(支給限度額)が決められています。
なお、上限を超えてサービスを利用するときは、超えたサービス利用額は、全額自己負担となります。
| 要介護度 | 利用限度額(月額) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
注)額は介護報酬の1単位を10円として計算。
注)福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。
介護保険被保険者証の取り扱いについて
要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されています。
施設サービスの費用について
介護保険施設に入所したときは、施設サービス費用の1割、2割、または3割のほかに、居住費、食費及び理美容などの日常生活費が、それぞれ全額自己負担となります。
- 利用者の負担の中で、居住費は居室の種類によって異なります。
- 要支援1・2と認定された方は、施設サービスを利用できません。
介護サービス利用者の負担軽減制度について
負担限度額認定申請
低所得の人の施設利用が困難とならないように、介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用したときの1日の居住費(または滞在費)と食費について、利用者負担段階が第1段階から第3段階までの人には、負担限度額を設定し、負担を軽減しています。
ただし、デイサービス、デイケアを除きます。
負担限度額認定は申請していただく必要があります。申請は、介護保険施設に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用している人に限らず、在宅(自宅など)で生活している人や介護保険施設に入所する予定の人、短期入所をする予定の人もできます。
➡ 介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/91KB]
| 利用者負担段階 | 段階別対象者 |
|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員に住民税がかからない場合 生活保護の受給者 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員に住民税がかからない場合で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が809,000円以下の人 |
| 第3段階(1) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が809,000円超120万円以下の人 |
| 第3段階(2) | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
●食費の負担限度額(1日)
第1段階・・・300円(300円)
第2段階・・・390円(600円)
第3段階(1)・・・650円(1,000円)
第3段階(2)・・・1,360円(1,300円)
※短期入所サービスを利用した場合は( )内の金額になります。
●居住費の負担限度額(1日)
| 区分 | 居住費(日額) 単位:円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | |
| 多床室 | 0 | 430円 | 430円 | 430円 |
| 従来型個室 |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,370円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。
高額介護(介護予防)サービス費
1割~3割の利用者負担額には上限が設けられており、その上限を超えた場合は、申請により、「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。
具体的には、同じ月に利用したサービスについて、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超える場合に対象となります。
令和3年8月利用分から現役並みの所得区分が細分化され、上限額の一部が変更となりました。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 | 課税所得 690万円 以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得 380万円 以上 690万円 未満 | 93,000円(世帯) | |
| 課税所得 145万円以上 380万円 未満 | 44,400円(世帯) | |
| 一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) | 44,400円(世帯) | |
| 住民税世帯非課税等 | 24,600円(世帯) | |
| 住民税世帯非課税等 且つ 以下の個人の方 ・老齢福祉年金の受給者 ・課税年金収入額 + その他の合計所得金額が809,000円以下の方 |
15,000円(個人) | |
| ・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(個人) 15,000円(世帯) |
|
社会福祉法人等による利用者負担の軽減
低所得者で、特に生計が困難な人が、軽減を申し出た社会福祉法人等のサービスを利用したときは、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。
●軽減の対象となるサービス
※軽減の申し出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみに適用されます。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護系サービス | 訪問介護 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 |
| 通所介護系サービス |
通所介護 |
| 短期入所系サービス | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 地域密着型介護老人福祉施設 |
|