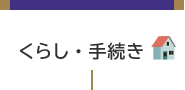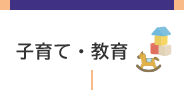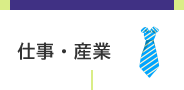本文
国民年金の制度・保険料について
年金のしくみについて
- 国民年金・厚生年金等の公的年金制度は、国が責任をもって運営しています。
- 日本の年金制度は、国民年金からすべての国民に、共通の基礎年金が支給され、厚生年金からは基礎年金に上乗せの報酬比例の年金が支給されるしくみをとっています。
- 基礎年金には、自営業者等だけではなく、厚生年金の加入者とその被扶養配偶者にも共通する給付として、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の3種類があります。
- 年金を受けられることになった人が手続きする場所は、年金制度への加入期間が国民年金の第1号被保険者のみの人は、市町村役場の国民年金の窓口、その他の人は最寄りの社会保険事務所等となっております。
また、年金は、受ける資格ができた月の翌月から、死亡等によって受けられなくなる月まで支給されます。 - 国民年金・厚生年金とも、2月、4月、6月、8月、10月および12月の年6回に分けて、前の2ヶ月分(たとえば4月の場合は2月と3月の2ヶ月分)の年金が、郵便局または銀行等の金融機関を経由して支払われます。
国民年金に加入する人
- 国民年金の加入者は、保険料を納める方法が違いますので、次の3種類に分けられています。
- 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農業、商工業などの自営業者等と学生。 - 第2号被保険者
厚生年金または共済組合等に加入している人。 - 第3号被保険者
第2号被保険者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者。
- 20歳になったとき、第1号被保険者に該当する人は、市町村の窓口で国民年金の加入者になるための手続きを必ず行ってください。
なお、平成3年4月から、20歳以上の学生も、第1号被保険者として国民年金に必ず加入することになっています。 - 第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金の加入者等)の配偶者のうち、健康保険の被扶養配偶者にあたる20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者となります。
- 第3号被保険者になると、配偶者が加入している厚生年金等から保険料が拠出されるため、自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。
なお、男性であっても、被扶養配偶者であれば、第3号被保険者に該当します。
国民年金の保険料について
- 国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1ヶ月当たりの保険料は17,510円です。(令和7年度)
- 毎月の保険料は、翌月の末日までに納めます。
保険料は、社会保険庁から送られてくる納付書で全国の金融機関(銀行、郵便局、農漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫)社会保険事務所、コンビニ等で納められます。希望すれば、これらの金融機関等で口座振替もできることになっています。
また、一定期間の保険料を前払いすると割引される「前納制度」があります。 - 保険料の免除を受けられる制度もあります。
・法定免除
生活扶助を受けていたり、障害基礎年金受給者は、届出によりその期間の保険料の全額が免除されます。
・申請免除
経済的な理由などから保険料を納めることが困難なとき、申請をして前年の所得に基づき承認を受けると保険料が全額または3/4、半額、1/4免除されます。その期間の老齢基礎年金は減額されますが、保険料の免除が承認された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して追納する制度があります。この申請は毎年度必要です。承認期間は7月分から翌年の6月分までです。
・学生納付特例制度
学生は、本人の所得が年間118万円以下の場合、申請し、承認されると在学期間の保険料が免除されます。この申請は毎年度必要です。承認期間は、4月分から翌年3月分までです。承認されなかった期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は受けられなくなることがありますのでご注意ください。
学生納付特例が承認された期間について
- 万一、在学中に重い障害が残ったときに障害基礎年金や、死亡したときに遺族基礎年金を受けるために必要な期間に含まれます。
- 老齢基礎年金を受けるために必要な期間に含まれます。ただし、年金額の計算には反映されません。
- 本来の納付期限後10年以内であれば、一定の金額を加算した保険料を納めることができます(追納制度)。追納した期間は老齢基礎年金の年金額の計算に含まれます。
国民年金の請求手続きについて
加入期間のすべてが第1号被保険者である人の老齢基礎年金、第1号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金および第1号被保険者の死亡による遺族基礎年金の請求手続きは、住所地の市町村役場で行います。加入期間に第2号被保険者期間や第3号被保険者期間がある人など上記以外の場合、年金の請求手続きは、社会保険事務所や共済組合で行います。
リンク先
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>