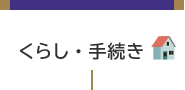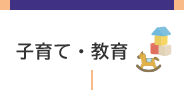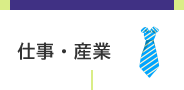本文
国民年金・厚生年金の切替について
20歳になったとき
国民年金には20歳〜60歳になるまで加入します。
住所のある市区町村役場の国民年金窓口で、本人が加入手続きをします。後日、年金手帳と納付書が社会保険事務所より送付されます。年金手帳は年金をもらうときに必要となりますので、無くさないようにしましょう。
会社に就職したとき
就職したら、厚生年金や共済年金に加入します。手続きは勤務先が行いますので、特に自分で手続きをする必要はありません。
会社を退職したとき
会社を退職すると、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをし、その後は国民年金に加入することになります。
変更手続きをしていないと、国民年金に未加入のまま、保険料も未納となってしまいます。手続きは退職日から14日以内に住所のある市区町村役場の国民年金窓口に年金手帳・印鑑・退職年月日を証明できるものを持参して行いますので、忘れずに手続きをしましょう。
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき
今まで第2号被保険者であった人も、配偶者の扶養となれば第3号被保険者に変わります。その手続きは配偶者の勤務先がすることになっていますから、本人の手続きは必要ありません。配偶者の勤務先へ届け出て下さい。
配偶者の扶養からはずれたとき
専業主婦だった人が再就職した場合には、第3号被保険者から第2号被保険者に変わります。この場合、勤務先が手続きをしますので、本人の手続きは不要です。ただし、自営業主になるなどの場合には第1号被保険者に変わりますので、住所のある市区町村役場の国民年金窓口へ年金手帳と印鑑を持って種別変更の手続きをしましょう。
配偶者が会社をかわったとき
たとえば、会社員の夫が転職して公務員になった場合でも、専業主婦である妻が第3号被保険者なのは変わりませんが、厚生年金から共済年金、あるいは共済年金から別の共済年金へ夫が転職した場合「第3号被保険者種別確認届」の提出が必要です。ただし、配偶者の勤務先を通して届け出るので、本人の手続きは不要です。
年金手帳をなくしたとき
年金手帳は令和4年4月より廃止となりました。基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したときは、基礎年金番号通知書の再交付を申請してください。
第2号被保険者は勤務先で社会保険事務所に再交付の書類を提出します。
第1号被保険者の場合には、市区町村役場で再交付の書類を提出します。