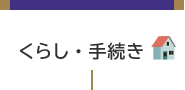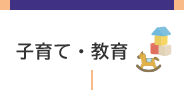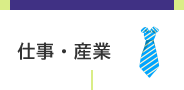本文
介護サービスの利用のしかた
介護サービスを利用するには申請が必要です
介護サービスを利用する場合、町に申請をして「介護や支援が必要である」と認定を受ける必要があります。
(1)申請
介護が必要であると感じたら、町住民福祉課の窓口に介護保険の保険証を添えて要介護認定の申請をしましょう。申請は、本人や家族のほか指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
(2)訪問調査
町の職員(介護認定調査員)が家庭を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族へ聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理されます(一次判定)。調査票に盛り込めない内容は特記事項として記入されます。
(3)審査・判定
町の依頼により主治医が傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会(穴水町には7人の委員がいます)が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。
(4)認定
町から、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。認定結果は、原則として30日以内に通知されます。
認定の有効期間は原則として新規は6ヶ月(最短3ヶ月、最長12ヶ月)、更新は12ヶ月(最短3ヶ月、最長48ヶ月)となります。なお、有効期間内に心身の状況が悪化した場合などは、認定の変更申請をすることができます。
要支援・要介護状態のめやす
| 状態区分 | 心身の状態の例 |
|---|---|
| 要支援1 | 状態の改善や悪化を防ぐことができると認定審査会で判断された方 |
| 要支援2 | 状態の改善や悪化を防ぐことができると認定審査会で判断された方(要支援1よりやや重度) |
| 要介護1 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要 など |
| 要介護2 | 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要 など |
| 要介護3 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある など |
| 要介護4 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある など |
| 要介護5 | 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある など |
| 非該当(自立) | 介護保険によるサービスを利用できませんが、町が行う保健・福祉事業によるサービスを受けることができます。 |