本文
センター長のささやき 第4話
第4話 能登半島地震が発生しました
突然の揺れと膨らむ焦り
公立穴水総合病院の能登北部呼吸器疾患センターを中心に能登北部の4公立病院で呼吸器疾患診療を開始して10年目を迎えた2024年1月1日。正月休みで福井の息子の家に滞在中の午後4時過ぎ、突然、家が揺れ、本棚が縦に小さく横に大きく揺れました。思わず両手で支えていました。結構長い時間と体感しました(坂井市は震度5弱とのちに判明)。ほぼ同時に、携帯とテレビから緊急アラームが鳴りました。能登北部を震源地とする大地震の発生です。
3年ほど前から、珠洲市近辺を震源地とした地震が微弱も含めて数えきれないほど発生していましたので、いよいよ来たかと思いました。テレビは地震・津波、次いで、輪島地区の大火災と矢継ぎ早に映像を映し出しますが、穴水病院とは連絡が取れずやきもきしました。不安な1月2日を迎えました。電源も途絶している状態なので在宅酸素の患者さんが気になります。1月3日、4日には先輩や友人から安否確認のSNS、メールが届きました。私が、穴水町に居り、被災したと思われたのであろう。
1月4日になっても公立4病院とは連絡つかず、午後に公立穴水総合病院の元事務局長のS氏に携帯電話がつながりました。「病院は大丈夫ですが、避難所にもなり、騒然としています。断水しており大変です。私も集落の避難所に避難して病院に顔を出しています。携帯(電話)が使えない場所があり困っています」とのこと。やはり、想像できないほどの混乱の中にあると思われる連絡でした。同日夜8時過ぎに、珠洲市総合病院院長とようやく連絡が取れました。「野戦病院化して、入院患者で対応困難な人や救急重症者は金沢地区の病院に移送している途中です。DMATが救急対応しているので、今のところ呼吸器科医は必要ないです。」とのこと。(後日判明しましたが、発災直後から、外傷患者や低体温症患者の救急受診に加え、避難者が公立4病院に押し寄せました。病院も断水と停電に見舞われ、検査機器なども作動せず、軽度の外科手術のみ可で、重症者を自衛隊やDMATが金沢地区などの医療施設に搬送しました。上下水道も使えず透析患者も同様に搬送しました。また、自宅の停電で在宅酸素療法(HOT)患者や持続陽圧呼吸療法を受けている睡眠呼吸障害患者も機器使用できず、電源や酸素ボンベを求めて病院に集中しました)。
病院長の言で一安心するも他の3病院とは全く連絡つかず、 東京の木田厚瑞先生に「病院の状況が不明なので、在京の酸素機器メーカー本社に応援協力を依頼してほしい」と連絡したところ、既に依頼したとのご返事をいただいた。金沢医科大呼吸器内科にも能登北部地区担当の在宅酸素機器メーカーに協力を要請してほしいと連絡しました(後日、帝人ヘルスケアなどの各社は独自に2日朝から能登地区に向かって酸素機器を掲載した救援車両を派遣していたことが判明しました。)。 日本呼吸器学会と日本呼吸ケア・リハビリテーション学会にも在宅酸素メーカー本社に支援要請を改めてお願いしました。
行きも帰りも悪夢の中
5日朝、丸岡インターから北陸自動車道に入り、金沢森本インターで降り、のと里山海道白尾インターへ向かいました。穴水町が目的です。金沢市内を走行中、穴水総合病院内科の先生から「石川県庁から先生に電話がはいりますので、不審電話と思わないで切らないでください」と電話がありました。直後に、県庁から電話入り「県庁に在宅酸素濃縮機器が20台ほど準備してありますので、必要なら連絡ください」とのこと。せめて、七尾まで、その機器を運んで、対応できるようにしておけばいいのにと正直に思いました。県庁も情報が錯そうして、どう対応してよいのか困っているであろうとも思い返しましたが。後日の、情報で、新型コロナ対策として、県庁が在宅酸素濃縮機器を用意していたとのこと。
のと里山海道は柳田インターまでしか通れず、降りて国道159号線、次いで、国道249号線に入るも、七尾市に近づくに連れ、緊急車両と一般車両が道路に満ちて、ノロノロ運転となりました。中能登町を過ぎると道路沿いの家屋倒壊が目立ち始め、道路には亀裂が縦横に入り、盛り上がりもあり、とても、スピードをだせない状況でした。これは、悪夢をみている感じでした。
対面して走行してくる救急車などの緊急車両もノロノロ運転です。運転手も救急隊員も早く目的病院につかないかと気が気ではないであろう。穴水町に近づくにつれ、倒壊家屋が増え、陥没した道路に車がはまり込んでおり、橋と接続する道路は段差ができ、電柱は傾き、マンホールは道路から大きく顔をだしており胸が痛くなりました。 穴水総合病院に普段の2.5倍の時間をかけて到着しました。
院内は補助電源で明かりはついてるものの、エレベーターも動かず、避難者が廊下や空病室にあふれていました(その後、一時800名に増加していたとのこと)。断水でトイレは使えないが、それでも使用したのであろう、臭気が漂っていました。病院職員の半分は病院にたどり着いていないという。救急室ではDMATが外傷患者の対応をしていました。内科の先生に外来で偶然出会いました。「1日から今までは、外科医が求められ内科医は無力でした」とのこと。院長を探すも会えず。5階まで階段を昇り私の部屋に入ると本とパソコンはひっくり返り、壁かけも落ちて、ガラス片も散乱して、ぐちゃぐちゃでした(資料7.)。
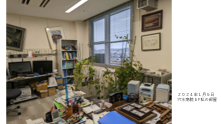 資料7. 公立穴水病院内5階の私の部屋
資料7. 公立穴水病院内5階の私の部屋
その後、病院の宿舎にたどり着くと、屋根瓦が落ちこぼれ、2階の部屋は雨漏りして、寝具は濡れ、1階の食器棚は倒壊し、風呂場の壁も崩れ、パソコンも崩れ落ち、冷蔵庫は扉が開き、食料が床に散乱していました(資料8.)。

 資料8. a.宿舎1階の台所 b.宿舎2階の居間 c. 屋根瓦が落ちた宿舎
資料8. a.宿舎1階の台所 b.宿舎2階の居間 c. 屋根瓦が落ちた宿舎
これは、住めない!と覚悟しました。管理課から、「帰れる場所で待機してください」と言われ、穴水から福井まで、また、長い時間をかけて戻るのかと思うと気が滅入りそうになりました。また、帰り着くことができるかとも不安になりましたが、午後4時ごろ、能越自動車道が、本日の午後に開通したとの連絡が入り、帰る決心をしました。
オオカミ少年になれなかった呼吸器専門医
ここ数年、何度も当該地区では地震が発生していたので、私自身も、「またか」と慣れてしまい、「治にいて乱を忘れず」という格言をすっかり忘失していました。呼吸器内科医である私自身、電源喪失の場合にHOT患者が「酸素難民」と化すということを啓発する考えに思い至らなかったのです。専門医失格です! もっと早い段階で地震対策(インフラの見直し補強)に地域自治体・行政も力をいれておくべきだったし、住民も危機対応への備えをしておくべきだつたと思います。すべて後の祭りです。そして、堅牢な建物の少ない過疎地の病院は貴重な避難場所になり、押し寄せる被災患者と避難者が混在し、自らも被災した医療者が休む暇なく対応を余儀なくされ、疲労困憊することが判明しました。 これまで、能登北部地区の病院は、避難所としての施設提供と飲料水や非常食糧などの提供の役割を想定してはいなかったのです。が、否応なしに、今回の災害時には、その役割を求められたことになりました。
振り返って東日本大震災時の当該地病院の事情はどうであったかと検索しますと、石巻赤十字病院の矢内医師らが既に同様の経験を報告し警鐘を鳴らしています5)。能登半島地震の規模が想定を超えていたと言い訳になりますが、オオカミ少年となる覚悟も私にはありませんでした。もともと、医療(人材)資源の少ない能登北部地区の公立病院は、経験ある中堅医師が慢性的に不足しており、自治医大卒業生と金沢大学医学部の地域枠卒業生の1年ごとの派遣でかろうじて人材を確保してきており、それと、金沢医科大・金沢大などからの非常勤医師の派遣とで診療レベルを何とか保ってきている状況でした。
今回の、災害対応では、医療者も医療施設も被災して、医療従事者も病院にたどり着けず、規定病床を減らして自衛隊6)、緊急消防援助隊7),災害派遣医療チーム(DMAT)8)(延べ1139隊活動)、全日本病院医療支援班(AMAT)9)(延べ29チーム、計121人)、 日本医師会災害医療チーム(JMAT)10)(延べ1097チーム、計3583人)、日本災害時透析医療協働支援チーム(JHAT)11)(延べ141人)災害支援検査技師12)(延べ405人)、日本病院薬剤師会13)(延べ84名)、日本薬剤師会14)(日薬スキームによる派遣者2395名、石川県薬剤師会による派遣者1701名) 災害支援ナース15)(日本看護協会 延べ2510人)、などの直接的な支援活動と、避難所や仮設住宅などへの日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)16)(延べ5500名以上が支援活動)や災害時感染制御チーム17)(DICT84名と14協賛企業)、災害看護メンバー18)(災害看護学会)などの諸支援によって、ぎりぎり病院の診療体制を維持していました。それでも、重傷(症)者やある程度専門性の必要とされる疾病患者を金沢地区の医療施設に転送するなど、当地の医療関係者の負担をできるだけ減らす工夫の上でです。
参考資料
1.呼吸eレポート 提言・論説 呼吸器医師不在地区での呼吸ケア展開-呼吸ケアと慢性呼吸器疾患看護認定看護師- 2019;3時38分-44.
2. 石川県医療計画 平成25年4月発行 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/center.html (accessed 2016年7月19日)
3. 石川県医療計画 平成30年4月発行 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/center.html (accessed 2019年7月19日)
4. 石川県医療計画 石川県健康福祉部地域医療推進室 令和6年8月 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/center.html 2024年10月5日アクセス
5. 矢内勝 東日本大震災における呼吸器診療の実際と課題 ワークショツプII 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2012;22時34分0-344
6. 防衛省・自衛隊 災害派遣について 令和6年能登半島地震への対応 https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2024/202401_ishikawa.html 2025年4月14日アクセス
7. 広域応援室 緊急消防援助隊情報 令和6年能登半島地震における緊急消防援助隊の活動について https://www.fdoma.go.jp>items>rei_0604_18 2025年4月14日アクセス
8. 石川県医療計画 石川県健康福祉部地域医療推進室 令和6年8月 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/center.html 2024年10月5日アクセス
9. 公益社団法人 全日本病院協会 AMAT事務局 令和6年能登半島地震AMAT活動報告 https://www.ajiヘクタール.or.jp>hms>amat>pdf 2025年2月9日アクセス
10. 10. 小川洋輔.JMATの活動が終了、医師1191人が支援に 能登半島地震から5カ月、石川県医師会会長が謝意. M3.comニュース 発表2024年5月31日 立方メートル.com /news/iryoishin/1212294 2024年12月15日アクセス
11. 山家敏彦 令和6年能登半島地震における日本災害時透析医療協同支援チームの活動と学び 2024年7月5日KAIT TOWNオーブン・イベント「能登半島地震の支援と私たちの災害対策」緊急報告会 https://kait-ccd.jp>wp-cintent>uploads>2024/07 2024年12月14日アクセス
12. 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 能登半島地震における活動報告書 P1-P31 令和6年4月25日 https://www.jamt.or.jp>noto-eq>docs 2024年11月7日アクセス
13. 薬事日報ウエブサイト 【日病薬】被災地で薬剤師82人が活躍―能登半島地震支援を終了 2024年4月11日 https://www.yakuji.co.jp>entry109715 2024年4月29日アクセス
14. 岩月進 令和6年能登半島地震における支援活動報告 公益社団法人日本薬剤師会 2024年8月7日 https://www.bousai.go.jp>noto>pdf>siryo3_2_9 2024年4月26日アクセス
15. 日本看護協会 令和6年能登半島地震 災害支援ナースを延べ2,510人派遣 協会ニュース2024年2月号 https://www.nurse.or,jp>home>about.kyoukainews 2024年4月26日アクセス
16. 一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会 令和6年能登半島地震災害リハビリテーション支援報告書 令和6年11月 jrat.jp/2634.html 2025年2月4日アクセス
17. 泉川公一 感染と微生物検査12 自然災害と感染症およびその対策 モダンメディア2024;70:22-27
18. 酒井明子、花房八智代、作川真悟 日本災害看護学会先遣隊 令和6年能登半島地震活動報告 2024年1月2日(火曜日)3日(水曜日) 一般社団法人日本災害看護学会 https://www.jsdn.gr.jp>moved.html 2024年4月26日アクセス
第5話 いよいよ混乱の渦の中です に続く


